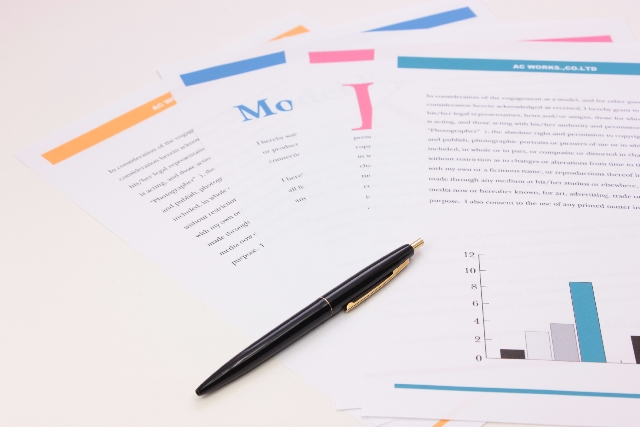


雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
私の場合と違うのかも知れませんが、最初訓練校に行こうと思い、助成金の手続きをしようと思ってハローワークに行ったのですが一応失業保険の方が適用になるか調べて見ますね。と言われみてもらったら、期間が足りないので無理です。みたいな事言われ、最終的にまた助成金の手続きに行った時には違う方に、失業保険出ますので、そちらが適用になります。と言われました。
ちなみに私の場合は最終的に働いてた期間が四ヶ月未満(社会保険に入らないといけないので期間終了って感じの退職になりました)その前が休み休みだったのですが半年未満で業績悪化で退職してます。
離職表を出したら会社都合退職ですぐ失業保険がでました。トピ主さんはA社とB社と会社都合と自主退職と退職理由が違うみたいなので多分ですが、10年勤務していたA社のみになるかと思います。B社は二ヶ月勤務だけのようですし、窓口で一度確認してみるか電話で問い合わせして見ればいかがでしょうか?
ちなみに私の場合は最終的に働いてた期間が四ヶ月未満(社会保険に入らないといけないので期間終了って感じの退職になりました)その前が休み休みだったのですが半年未満で業績悪化で退職してます。
離職表を出したら会社都合退職ですぐ失業保険がでました。トピ主さんはA社とB社と会社都合と自主退職と退職理由が違うみたいなので多分ですが、10年勤務していたA社のみになるかと思います。B社は二ヶ月勤務だけのようですし、窓口で一度確認してみるか電話で問い合わせして見ればいかがでしょうか?
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
関連する情報